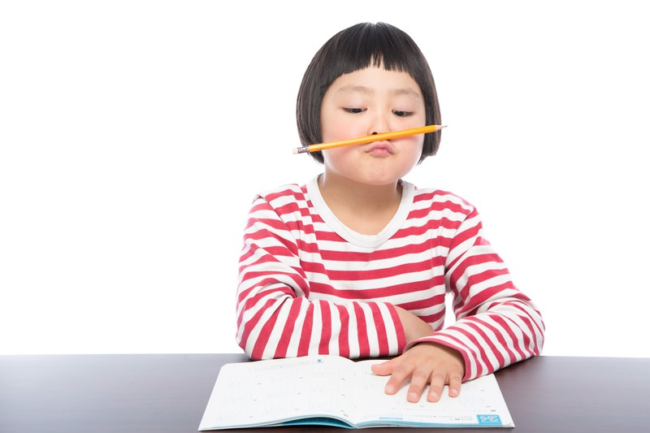もとさぶ
もとさぶ
「直前資料を見るべきか、見なくてもいいか」について管理人の見解を述べた記事は下記事となります。
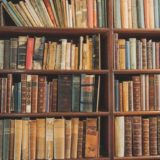 一級建築士試験 当日配布される学科要点【直前資料】は見るべき?
一級建築士試験 当日配布される学科要点【直前資料】は見るべき?注意①:「直前資料」という名称は管理人が勝手につけたネーミングです
注意②:直前資料は2014年度の時のもので、なおかつ、日建学院の直前資料しか持っていません
注意③:注意②より「2014年度がたまたま的中しているだけで、その他の年度が不明である」「他学校の直前資料ではどうだったのかが不明である」
以上の点はご了承ください
 もとさぶ
もとさぶ
- 「2014年度 日建直前資料問題」と「2014年度 本試験問題」の類似問題について
直前資料問題と本試験問題の類似問題の比較検証
前回のおさらいとして…まずは「直前資料から出題された問題数」を載せておきます。
計画:5/20(25%)
環境・設備:5/30(16.6%)
法規:未調査
構造:16/50(32%)
施工:8/50(16%)
 もとさぶ
もとさぶ
直前資料の文章内容は全て【正しい】です。
「太文字」「赤文字」は重要キーワードを示します。
下段:本試験の文を記載
本試験は全て【問題文】を記載しています。
問題文の前には「当時の設問番号」と「正誤」を記載しておきます。
上段、下段共に原文そのままで記載しています
計画の比較
 もとさぶ
もとさぶ
1/5
中層集合住宅において、光井戸(light well)と呼ばれる吹抜けを設けることにより、住戸の奥行きが深い場合にも、通風と採光を得ることが出来る。
ライトウェルは住戸の奥行きが深場合であっても、通風と採光を得ることができる計画手法である。
2/5
図書館におけるBDS(ブックディテクションシステム)は、電波や磁気を利用して貸出処理されていない資料の館外への持ち出しを感知するシステムである。
図書館の計画に当たり、閉架式書庫の内部にブラウジングルームを設け、BDSによって、入室管理を行うことができるようにした。
3/5
多機能便房の広さについて、折りたたみ式シートの設置及び介助スペースを考慮して、200cm×200cmとした。
多目的トイレにおいて、内法寸法を2000mm×2000mmとし、オストメイト用の流しや車椅子使用者が利用できる洗面台を設置した。
4/5
LCC(ライフサイクルコスト)は、建築物や建築設備システムの建設から廃棄に至るまでに要する総費用で、一般に、建設費・保守管理運転費・撤去処分費の合計として求められる。
LCMは、建築物の機能や効用の維持又は向上を図りつつ、建築物をその生涯にわたって管理することであり、LCCを最大化することが大きな目的である。
5/5
「所要数量」は、「定尺寸法による切り無駄」や「施工上やむを得ない損耗」を含んだ数量である。
「所要数量」は、「定尺寸法による切り無駄」や「施工上やむを得ない損耗」を含んだ数量をいい、鉄筋、鉄骨、木材等の数量がこれに該当する。
2/5のBDSの出題文を見るとあまり似ていないのですが、BDSの意味をしっかりと理解していれば解ける問題です。
他の科目でもこういった問題は「類似問題」と解釈をしています
環境・設備の比較
直前資料の文章内容は全て【正しい】です。
「太文字」「赤文字」は重要キーワードを示します。
下段:本試験の文を記載
本試験は全て【問題文】を記載しています。
問題文の前には「当時の設問番号」と「正誤」を記載しておきます。
上段、下段共に原文そのままで記載しています
1/5 室内に同じ音響出力をもつ二つの騒音源が同時に存在するとき、室内の音圧レベルは、騒音源が一つの場合に比べて約3db増加する。 2/5 受水タンクの保守点検スペースは、周囲・下部は60cm以上、上部は100cm以上を確保する。 3/5 給水管内の水の流れを急激に停止させると、ウォーターハンマーが起こりやすい。 4/5 予作動式の閉鎖形スプリンクラー設備は、ヘッドとは別に設ける感知器と連動して予作動弁を開き散水する方式であり、誤作動による被害が許されない電算室等に適している。 5/5 連結送水管の放水口は、消防隊が有効に消化活動を行うことができるように、階段室や非常用エレベーターの乗降ロビー等に設置する。 直前資料の文章内容は全て【正しい】です。 下段:本試験の文を記載 本試験は全て【問題文】を記載しています。 上段、下段共に原文そのままで記載しています 1/16 純ラーメン構造の中高層建築物において、地震時の柱の軸方向力の変動は、一般に、中柱よりも隅柱のほうが大きい。 2/16 腰壁や垂れ壁の付いた鉄筋コンクリート構造の柱(短柱)は、一般に、それらの付かない同一構面内の柱に比べて、地震時の塑性変形能力が小さく、先に破壊しやすい。 3/16 許容応力度は、標準貫入試験のN値が同じ場合、一般に、砂質地盤よりも粘土地盤のほうが大きい。 4/16 保有水平耐力の算定に当たって、一般構造用鋼材がJIS規格品であれば、鋼材の材料強度の基準強度を割増しすることができる。 5/16 部材断面を構成する板要素の幅厚比を大きくすると、局部座屈が生じやすくなる。 6/16 節点の水平移動が拘束されていないラーメン構造の柱材の座屈長さは、一般に、その柱材の節点間距離よりも長くなる。 7/16 箱形断面の梁は、一般に、横座屈を起こさないと考えて設計することができる。 8/16 地震時の水平力を負担する筋かい材の接合部の破断耐力が、筋かい軸部の降伏耐力より十分に大きくなるようにした。 9/16 山形鋼を用いた筋かい材の有効断面積の計算において、筋かい材の断面積からファスナー孔による欠損部分及び突出脚の無効部分の断面積を差し引く。 10/16 柱の帯筋は、せん断補強のほかに、帯筋で囲んだコンクリートの拘束と主筋の座屈防止に有効である。 11/16 3階建の建築物において、隅柱は、接合部を通し柱と同等以上の耐力を有するように補強した場合、通し柱としなくてもよい。 12/16 地震力に対する耐力壁の所要有効長さは(必要壁量)は、はり間方向とけた方向で同じ値となる。 13/16 含水率が繊維飽和点以下の木材において、乾燥収縮率の大小関係は、年輪の接線方向>半径方向>繊維方向である。 14/16 木材の強度は、一般に含水率が増加すると低下し、繊維飽和点以上では一定となる。 15/16 コンクリートのヤング係数は、一般に、コンクリートの圧縮強度が高いほど大きい値となる。 16/16 鋼材は、炭素含有量が0.8%程度までは、炭素含有量が増すとともに、引張強さ、降伏点は大きくなるが、破断伸びは小さくなる。
音源の音響パワーを50%に下げると、受音点の音圧レベルは約3db下がる。
飲料用受水槽の側面、上部及び下部に、それぞれ60cmの保守点検スペースを設けた。
給水圧力が高すぎると、給水管内の流速が速くなり、ウォーターハンマー等の障害が生じやすい。
予作動式の閉鎖型スプリンクラー設備は、非火災時の誤放水を避けるため、衝撃等でスプリンクラーヘッドが損傷しても散水を抑える構造となっている。
連結送水管の放水口は、建築物の使用者が火災の初期の段階において直接消火活動を行うために設置する。構造の比較
「太文字」「赤文字」は重要キーワードを示します。
問題文の前には「当時の設問番号」と「正誤」を記載しておきます。
純ラーメン構造の中高層建築物において、地震時の柱の軸方向力の変動は、一般に、外柱より内柱の方が大きい。
柱のせん断破壊を防止するために、柱せいに対する柱の内法高さの比を大きくし、短柱とならないようにした。
地盤の許容支持力度は、標準貫入試験のN値が同じ場合、一般に、砂質地盤より粘土質地盤の方が大きい。
Quの算出において、鉄筋コンクリート構造の梁の曲げ強度を算定する場合、主筋にJIS規格品のSD345を用いれば、材料強度を基準強度の1.1倍とすることができる。
梁に使用する材料をSN400BからSN490Bに変更したので、幅厚比の制限値を大きくした。
横移動が拘束されているラーメン架構において、柱材の座屈長さを節点間距離と等しくした。
角形鋼管を用いて柱を設計する場合、横座屈を生じるおそれがないので、許容曲げ応力度を許容引張応力度と同じ値とした。
引張力を負担する筋かいにおいて、接合部の破断強度は、軸部の降伏強度に比べて十分に大きくなるように設計する。
山形鋼を用いた引張力を負担する筋かいの接合部に高力ボルトを使用する場合、山形鋼の全断面を有効として設計する。
鉄筋コンクリート構造の柱の帯筋は、せん断補強のほかに、帯筋で囲んだコンクリートの拘束や主筋の座屈防止に有効である。
隅柱は、接合部を通し柱と同等以上の耐力を有するように補強した管柱とした。
平面が長方形の建築物において、地震力に対する必要な耐力壁の有効長さ(必要壁量)を張り間方向及びけた行方向について同じ値とした。
木表は、一般に、木裏に比べて乾燥収縮が大きいので、木表側が凹に反る性質がある。
木材の強度は、一般に、気乾比重が小さいものほど大きい。
コンクリートのヤング係数は、コンクリートの気乾単位体積重量又は圧縮強度が大きいほど、大きい値となる。
鋼材は、一般に、炭素含有量が多くなるほど、破断に至るまでの伸びが小さくなる。
施工の比較
 もとさぶ
もとさぶ
直前資料の文章内容は全て【正しい】です。
「太文字」「赤文字」は重要キーワードを示します。
下段:本試験の文を記載
本試験は全て【問題文】を記載しています。
問題文の前には「当時の設問番号」と「正誤」を記載しておきます。
上段、下段共に原文そのままで記載しています
1/8 建築士法に基づき、建築物の工事監理を終了した場合、直ちに、「工事監理報告書」を、建築主あてに提出する。 2/8 砂質土地盤の床付け面を乱してしまった場合、転圧による締固めが有効である。 3/8 既製コンクリート杭を用いた打込み工法において、打込み完了後の杭頭の水平方向の施工精度の目安値については、杭径の1/4以内、かつ、100mm以内とした。 4/8 場所打ちコンクリート杭において、泥水中に打込むコンクリートの単位セメント量は、330kg/㎥以上とする。 5/8 径が同じ異形鉄筋の相互のあきについては、「呼び名の数値の1.5倍」、「粗骨材の最大寸法の1.25倍」、「25mm」のうち、最も大きい数値以上とする。 6/8 設計基準強度が60N/㎟の高強度コンクリートの場合、コンクリートの練混ぜから打込み終了までの時間については、外気温に関わらず120分を限度とする。 7/8 高力ボルト接合おいて、接合部材間に1mmを超えるはだすきが生じる場合は、フィラープレートを挿入してはだすきを埋める。 8/8 溶接部の受入検査における表面欠陥及び精度の目視検査は、特記がない場合、抜取検査とし、溶接の部位や種類ごとにロットを構成し、それぞれのロットから10%に相当する部材数を検査対象としてサンプリングする。 個人的に直前資料の内容は「過去問で見た事のある問題が多い」という印象だった 以上で検証を終えます。
共同住宅の工事監理を終了したので、直ちに、「工事監理報告書」を建築主あてに提出した。
粘性土地盤の床付け面を乱してしまったので、礫・砂質土に置換して締め固めた。
既製コンクリート杭を用いた打込み工法において、打込み完了後における杭頭の水平方向の施工精度の目安値については、杭径の1/4以下、かつ、100mm以下とした。
場所打ちコンクリート杭工事において、安定液に打ち込む杭に使用するコンクリートの単位セメント量については、310kg/㎥とした。
径が同じ異形鉄筋の相互のあきについては、「呼び名の数値の1.5倍」、「粗骨材の最大寸法の1.25倍」、「25mm」のうち、最も大きい数値以上とした。
設計基準強度が60N/㎟の高強度コンクリートにおいて、コンクリートの練混ぜから打込み終了までの時間の限度については、外気温にかかわらず、原則として、120分とする。
高力ボルト接合において、接合部に生じた肌すきが0.5mmであったので、フィラープレートを挿入しなかった。
溶接部の受入検査における表面欠陥及び精度の検査は、特記がなかったので、目視による抜取検査とし、溶接の部位や種類ごとにロットを構成し、それぞれのロットから10%に相当する部材数を検査対象としてサンプリングした。まとめ
 もとさぶ
もとさぶ ピヨひこ
ピヨひこ もとさぶ
もとさぶ
直前資料を「貰う・貰わない」の判断材料になれば嬉しいです。