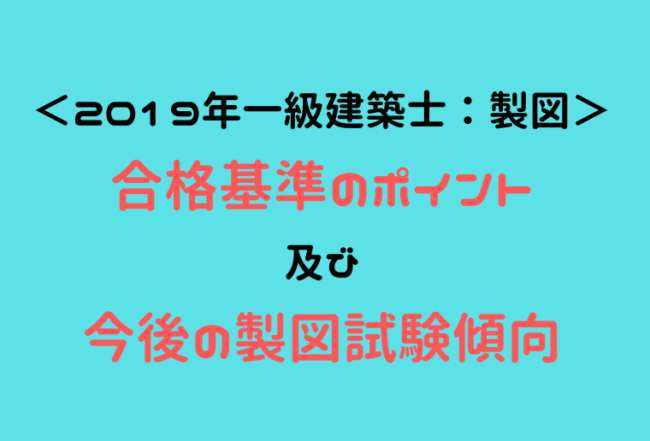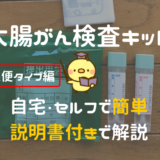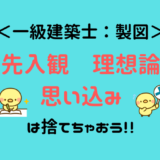令和元年(2019年度)12月19日に一級建築士製図試験の合格者、つまり一級建築士試験の合格者の発表がありました。
公益財団法人 建築技術教育普及センターのHPでは「(設計製図試験の)合格者の受験番号」と「(設計製図試験の)合格者の発表について」が掲載されます。
 ピヨひこ
ピヨひこ
今回記事は「合格者の発表について(合格基準のポイント)」で【気になった点】【これからの製図試験傾向】についての見解を述べていきたいと思います。
 もとさぶ
もとさぶ
- 令和元年(2019年度)の製図試験:合格基準のポイントで気になった点
- 今後の製図試験傾向
令和元年(2019年度)の製図試験:合格基準のポイントで気になった点
私がものすごく気になった点は以下の3点です。
- 製図試験の合格率が低かったということ
- 「図面ランクⅡが3.0%」で図面ランクⅡに該当する人が非常に少ないということ
- 【設計条件・要求図面等に対する重大な不適合】として「PS・DS・EPS」が加わったということ
合格率の低さについて
まずは令和元年(2019年)~平成26年(2014年)までの合格率を見ていきましょう。
-令和元年~平成26年までの合格率-
| 年度 | 学科合格率 | 製図合格率 | 総合合格率 |
| 令和元年・10月 (2019年) | 22.8% | 36.6% | - |
| 平成30年 (2018年) | 18.3% | 41.4% | 12.5% |
| 平成29年 (2017年) | 18.4% | 37.7% | 10.8% |
| 平成28年 (2016年) | 16.1% | 42.4% | 12.0% |
| 平成27年 (2015年) | 18.6% | 40.5% | 12.4% |
| 平成26年 (2014年) | 18.3% | 40.4% | 12.6% |
 ピヨひこ
ピヨひこ
-令和元年~平成26年までの図面ランクⅠ~Ⅳの割合-
| 年度 | ランクⅠ | ランクⅡ | ランクⅢ | ランクⅣ |
| 令和元年・10月 (2019年) | 36.6% | 3.0% | 29.2% | 31.3% |
| 平成30年 (2018年) | 41.4% | 16.3% | 16.5% | 25.9% |
| 平成29年 (2017年) | 37.7% | 21.2% | 29.9% | 11.2% |
| 平成28年 (2016年) | 42.4% | 27.1% | 20.7% | 9.7% |
| 平成27年 (2015年) | 40.5% | 25.2% | 23.3% | 11.0% |
| 平成26年 (2014年) | 40.4% | 32.8% | 20.5% | 6.3% |
製図試験の合格率が低くなってしまった理由について
令和元年(2019年)製図試験の「合格率・ランクⅠ・ランクⅡ」の割合が例年より低くなってしまった理由は以下が考えられます。
- 令和元年(2019年)学科試験の合格率が例年より高かったから
- 重大な不適合として「PS・DS・EPS」が追加されていたから
 もとさぶ
もとさぶ
以前までの製図試験では「PS・DS・EPS」はどう捉えられていたか
 ピヨひこ
ピヨひこ
以前までの製図試験だと「PS・DS・EPS」はあくまで減点程度の項目だったと予想します。
総合資格の自己採点用チェックシートでも「PS・DS・EPS」は減点程度の扱いでした。
今後の製図試験の傾向
今まで減点項目だと思っていた「PS・DS・EPS」ですが、冷静に考えてみれば建物には必要な設備です。
別の記事でも書いていますが、近年の製図試験傾向として「建物が成立しているかどうか」が合格の基準となってきている気がします。
なので、記載(指定)のない部分にも細心の注意を払い【建物に必要となる要素はしっかり抑えて記入する】ということが、製図試験に合格する為の鍵となるでしょう。
 もとさぶ
もとさぶ
以後の製図試験はPS・DS・EPSは「重大な不適合」として扱われることを忘れずに、かつ、その他の点でも「建物として成立するのかどうか」という部分を意識しながら頑張っていきましょう。